|
1. なぜ、技能統合の授業か?
中学校・高等学校英語科の学習指導要領改訂において、「4技能を統合的に活用できるコミュニケーション能力を育成する」ことは、改訂の基本方針の柱の一つとされている。日常生活で行われるコミュニケーションでは、母語、外国語を問わず、単一の技能だけで完結することは少なく、複数の技能が関連することが普通であることからも技能統合の必要性は理解できる。そこで、高島(2011)が指摘するように、学習者は、「技能統合型言語活動」を通して、現実場面で行われるコミュニケーションを教室内で疑似体験することが必要となる。技能統合の授業を通して、4技能の総合的な育成を目指すのである。
本連載第1回~第3回では、中学校において複数技能を統合して行う授業の具体的な例として、指導で必要となるワークシートの例やより詳細な事例を、ウェブページと併せて紹介しながら、4技能統合の英語授業で使えるアイデアを提供したい。
2.技能統合の授業は、学習指導要領の“New Face”?
中学校の新学習指導要領では、「言語活動」の中で、技能統合について次のように具体的に指導事項を示している。衆知のように、それらのほとんどは、旧学習指導要領において取り上げられていた事項と大きな違いはない。ちなみに、右に示した指導事項のうち下線を付した部分のみが、今回の改訂で新たに加えられた内容である。
 |
 |
●「聞くこと」
話し手に聞き返すなどして内容を確認しながら理解すること。
<「聞くこと」+「話すこと」の統合>
●「話すこと」
聞いたり読んだりしたことなどについて、問答したり意見を述べ合ったりなどすること。
<「聞くこと」「読むこと」+「話すこと」の統合>
●「読むこと」
話の内容や書き手の意見などに対して感想を述べたり賛否やその理由を示したりなどすることができるよう、書かれた内容や考え方などをとらえること。
<「読むこと」+「話すこと」「書くこと」の統合>
●「書くこと」
聞いたり読んだりしたことについてメモをとったり、感想、賛否やその理由を書いたりなどすること。
<「聞くこと」「読むこと」+「書くこと」の統合>

(平成20年版中学校学習指導要領 「2 (1)言語活動」より) |
|
 |
 |
つまり、技能を統合した授業や言語活動は、今回の改訂による“New Face”ではなく、以前から示されていた指導事項であり、今回の改訂では、これまでの指導を継続し、さらにそれらを充実させることが求められていることがわかる。
3. 技能統合の授業で目指すもの
技能統合の授業では、単に複数の技能を並べてつなげれば、学習者にとって有益であるということではない。各技能を「有機的に関連づける」ことが重要であり、実際のコミュニケーションに近い言語活動が教室内に作り出され、学習が促進されるように意図した技能統合が求められているのである。
また、旧学習指導要領における言語活動に比べ、一歩踏み込んだ言語活動を行うことが求められる。例えば、今回の改訂では、小学校英語活動の実施を踏まえ、「聞くこと」「話すこと」の目標から「慣れ親しむ」という事項が除かれた。これにより、中学校での「聞くこと」「話すこと」を統合した言語活動では、「慣れ親しむ」段階を超えた言語活動が求められている。さらに、高校の「英語表現Ⅰ」では、「即興で話す」言語活動がその内容に示されており、その間をつなぐ中学校では、聞いた内容に即応して話すためのコミュニケーション力の基礎を養う技能統合授業が目指されることになる。そのほかの技能統合においても、授業時数の増加や扱う語彙の増加もあり、これまでの指導に比べ、より深まりのある言語活動の充実が図られなければならない。
4. 「書くこと」「話すこと」を統合した授業
技能の統合を意識するしないにかかわらず、これまでも最も頻繁に自然な指導の流れとして行われていたのが、「書くこと」と「話すこと」の統合であろう。第1回の本稿では、この「書くこと」と「話すこと」の統合について考えたい。例えば、スピーチの原稿を準備し(「書くこと」)、それをもとにして英語でスピーチを行う(「話すこと」)などはその例である。中学校段階では、準備せずに即興で英語による「発表」を行うことは、学習者にとって非常にハードルが高く、負担が大きい活動となる。たとえ、短い英文でヒントを出題するクイズのような活動でも、多くの場合は英語でヒント作りを行い、準備し(「書くこと」)、それを、口頭練習したあとに実際にクラスの前で出題する「話すこと」)など、「書くこと」と「話すこと」の技能を統合し、ステップを踏んで実践している。
ここでは、まず、準備→練習→発表という指導の流れの中で、「書くこと」と「話すこと」を統合した「What am I? クイズSHOW」の実践を紹介する。さらに、準備→練習→発表という指導の流れの中に「読むこと」と「書くこと」、「聞くこと」と「話すこと」を統合させた「お勧め旅行プランを売り込もう」の実践を紹介する。
①「What am I? クイズSHOW」の実践
中学1年生でも実施可能な「書くこと」と「話すこと」を統合した授業である。5、6名の生徒で1グループを作ってクイズの出題者となり、英語でヒントを出していく。ヒントを聞いた同級生は、出題者が何について説明しているのかを当てる活動である。様々な活動のバリエーションが考えられるが、ここで紹介するのは、各グループでクイズを持ち寄り、クラス全体で「クイズSHOW」を行う活動である。出題グループ内では、それぞれが作ったクイズ(「書くこと」)を持ち寄り、どの問題をグループの出題問題にするか選択する。司会者(MC)およびヒントの発表者の役割を決め、ヒントは1人につき1つずつ発表するにように分担する。出題グループは、それぞれのセリフやヒントを書いて準備し、同級生は解答用紙にWhat am I?の答えを書いて解答する、という活動である。出題グループを順に交代して、どのグループも一度は出題者となるようにする。問題作りからクイズSHOWの実施も含め、3~4時間かけた実践である。下の例は、クイズSHOWの進行の様子である。
MCの生徒 : Welcome to our quiz show! Please listen to us. We have five hints. S1, you go first!
Student 1 : Hint No.1. I am in convenience stores. You can buy me at convenience stores.
Student 2 : Hint No.2. I am triangle. My shape is triangle.
Student 3 : Hint No.3. I am very soft. (with gesture)
Student 4 : Hint No.4. My color is white outside.
Student 5 : Hint No.5. I have some tuna, mayonnaise, tomato, lettuce, cucumber, egg or ham inside.
MCの生徒 : What’s the answer? Write down the answer, please.(解答記入の間)Who knows the answer?
挙手したS : Is it a sandwich?
MCの生徒 : That’s right! Well done! |
|
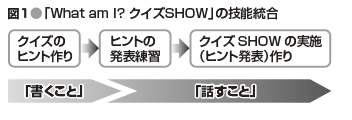 前の例は、クイズの問題を「書いて」準備し、「話して」伝える活動であり、「準備→練習→発表」という流れで進行していく。複数の技能が順を追って直列に並ぶタイプである。 前の例は、クイズの問題を「書いて」準備し、「話して」伝える活動であり、「準備→練習→発表」という流れで進行していく。複数の技能が順を追って直列に並ぶタイプである。
これに対して、次に紹介する例は、「書いて」準備し、「話して」伝える「準備→練習→発表」という流れではあるが、「書いて」準備する段階に「読むこと」が統合され、さらには、「話して」伝えた内容について生徒同士が「問答したり、意見を述べ合ったり」することで、「聞くこと」「話すこと」を統合させた実践である。
② 「お勧め旅行プランを売り込もう」の実践
 岐阜県大垣市立星和中学校の3年生を対象とした「お勧め旅行プランを売り込もう」の実践を紹介する。星和中学校は、校区内の小学校2校と連携して英語教育の小中連携に関して研究開発に取り組んできた学校である。 岐阜県大垣市立星和中学校の3年生を対象とした「お勧め旅行プランを売り込もう」の実践を紹介する。星和中学校は、校区内の小学校2校と連携して英語教育の小中連携に関して研究開発に取り組んできた学校である。
「お勧め旅行プランを売り込もう」は、3人1組で行われる活動である。3人のうちの2人が旅行会社の社員役となり、それぞれの旅行会社のお勧め旅行プランを売り込み、残り1人のお客役の生徒は2社のプランを聞き、どちらのプランが良いかを決めるという活動である。活動の流れは図2のようにまとめられる。この活動をグループ内で役割を交換しながら3セット行い、グループ内の全員が売り込み役とお客役を行うようにする。
旅行会社A社、B社を代表する2人は、それぞれの会社が推薦する海外旅行プランの英語によるプレゼンを行う。プランの特徴ができるだけお客に伝わるように、見学ポイント(places to see)、食事(food to eat)、現地での活動(things to do)などの情報を含めて、聞き手の興味を引きながら2分間の持ち時間内で説明を行う(活動1、2)。残りのお客役の1人は、2社の説明を聞いたあとにプラン内容について自由に質問し(活動3)、プレゼンから得た情報とそのあとのQ&Aの内容から、より魅力的だと思われるプランを選ぶ(活動4)。下の例は、フランスの旅行プランを紹介した生徒の例である。
Hello! I am from ○○ travel. Today I will show you a good travel plan. OK? (OK.) Do you know France? France is a famous country in Europe because there are many things to see. Do you know this? (エッフェル塔の写真を示して) (No, I don’t.) This is the Eiffel Tower. Eiffel Tower is the famous tower in the world. I want you to go up to the top of the tower. You can eat a special dinner course there. Special dinner course! OK? (OK.)
Do you like sweets? (Yes, I do.) This is a macaroon.(マカロンの写真を指して) Macaroon is a very delicious and colorful sweets. If you want, you can eat it. It is made by a special pâtissier(パティシエ). This is a beef steak, a large beef steak. If you want it, you can eat it and you will be very happy. OK? (OK.) Do you like fashion? (Yes, I do.) This is a dress made by Louis Vuitton. Do you know Louis Vuitton? (Yes. ) Louis Vuitton is a famous fashion brand. So I’m sure you like it. Do you know this?(モン・サン・ミッシェルの写真を示して) (No, I don’t.) This is Mont Saint-Michel. Mont Saint-Michel is a very famous world heritage site. If you want, you can buy a macaroon there. I’m sorry, time’s up! Let’s go to France! I am sure you like it!
( )内は、客役の生徒の発話
|
|
この活動に至るまでの一連の指導は、10数時間かけたプロジェクトであるが、「準備」(「書くこと」)→「練習」→「発表」(「話すこと」)という具合に、技能統合においては先に紹介したクイズの活動と同様の過程をたどる。しかし、「旅行プラン」の活動では、発表の内容を「書いて」準備する段階で、「読むこと」との統合も図られている。下は、生徒の「売り込みの原稿」の例であるが、原稿作りにあたり、教科書の本文を参照するように指示されていることがわかる。教科書の当該の課は、様々な国の見所を紹介する内容であり、生徒が原稿を作成するにあたって格好のモデルとなる教材であった。教科書内容の学習が進行するのと併行して、生徒は旅行プラン紹介の原稿の内容や英語表現を充実させていった。さらに、「Speed Input」という音読練習用のワークシートにも、売り込みに使える関連した内容や表現を扱い、生徒が原稿作成をする上での材料となっている。
教師は、生徒が教科書本文や「Speed Input」を読み、その中から自らの発表内容に生かせそうな表現を見つけ出し、原稿に加えていくように指導している。つまり、原稿を準備する段階で「読むこと」と「書くこと」を統合し、より豊かな内容と、より伝わりやすい英語表現になるように、教科書本文などの英文を読ませる工夫を加えているのである。
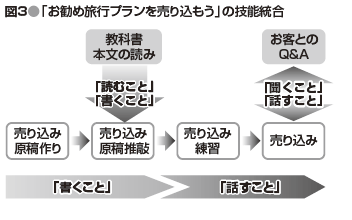 さらに、A社、B社のプレゼン後の「お客とのQ&A」では、お客がプランの内容について興味を持ったこと、さらに知りたいことなどを旅行社に質問し、追加情報を得る。ここでのお客と旅行社のやりとりは、「聞くこと」と「話すこと」が統合された活動である。しかも、この質疑応答はまったくの即興であり、学習者はそれまでに身につけた英語力を総動員して、コミュニケーションを図ることとなり、新学習指導要領で求められる一歩踏み込んだ言語活動となっている。 さらに、A社、B社のプレゼン後の「お客とのQ&A」では、お客がプランの内容について興味を持ったこと、さらに知りたいことなどを旅行社に質問し、追加情報を得る。ここでのお客と旅行社のやりとりは、「聞くこと」と「話すこと」が統合された活動である。しかも、この質疑応答はまったくの即興であり、学習者はそれまでに身につけた英語力を総動員して、コミュニケーションを図ることとなり、新学習指導要領で求められる一歩踏み込んだ言語活動となっている。
「お勧め旅行プランを売り込もう」の技能統合について、図3のようにまとめることができる。
<「お客とのQ&A」の例>
Q: Can I see beautiful nature?
A社:Yes, you can. This is the Palace of Versailles. Versailles has a very huge garden. So you can see a very beautiful garden.
B社:Sorry, no beautiful nature but you can go up to the top of the Statue of Liberty and you can see the view.
Q: Can I see a beautiful night view?
A社:Yes, you can. You can go up to the top of Eiffel Tower and you can see a very beautiful night view in France. I’m sure you like it.
B社:You can see a beautiful night view from the bridge.
Q: I want to eat delicious food. Do you have delicious food?
A社:Yes, we do. You can eat a very special French course. If you eat it you can become very happy and full.
B社:A社 said this food is very delicious(A社とB社の料理の写真を交互に指して) but this big American hamburger is more delicious! |
|
まとめ
今回は、「書くこと」「話すこと」の統合を中心に、それらに、「読むこと」や「聞くこと」を有機的に関連させた実践例を紹介した。星和中学校の実践では、「読むこと」と「書くこと」の統合によって、学習者が主体的に英語の表現に注目し、読んだあとに自らが表現することを意識した読みが行われている。また、旅行プラン説明のあとに自由Q&Aタイムを設けることで、「聞くこと」と「話すこと」が統合され、準備された発話に加え、一部分ではあるが、即興的な対応を求められるような一連の学習過程が仕組まれている。これにより、単に「準備→発表」のために「書くこと」と「話すこと」を結びつけた技能統合にとどまらず、実際のコミュニケーションにより近い場面で学習することを可能にした実践である。
次回は、4技能をフルに活用して行う「Reporting」の活動について紹介する予定である。
 参考文献 参考文献

●文部科学省(2008)『中学校学習指導要領解説 外国語編』開隆堂出版
●文部科学省(2010)『 高等学校学習指導要領解説 外国語編・英語編』開隆堂出版
●大垣市立星和中学校他(2011)「英語科におけるコミュニケーション能力の基礎を確実に身につけるための指導と評価のあり方」『教育研究開発事業(英語教育関係)公表会 研究紀要』
●高島英幸(2011)『英文法導入のための「フォーカス・オン・フォーム」アプローチ』大修館書店 |
|

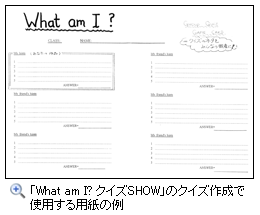

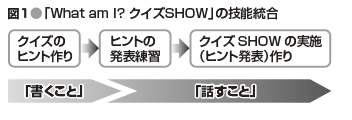 前の例は、クイズの問題を「書いて」準備し、「話して」伝える活動であり、「準備→練習→発表」という流れで進行していく。複数の技能が順を追って直列に並ぶタイプである。
前の例は、クイズの問題を「書いて」準備し、「話して」伝える活動であり、「準備→練習→発表」という流れで進行していく。複数の技能が順を追って直列に並ぶタイプである。 岐阜県大垣市立星和中学校の3年生を対象とした「お勧め旅行プランを売り込もう」の実践を紹介する。星和中学校は、校区内の小学校2校と連携して英語教育の小中連携に関して研究開発に取り組んできた学校である。
岐阜県大垣市立星和中学校の3年生を対象とした「お勧め旅行プランを売り込もう」の実践を紹介する。星和中学校は、校区内の小学校2校と連携して英語教育の小中連携に関して研究開発に取り組んできた学校である。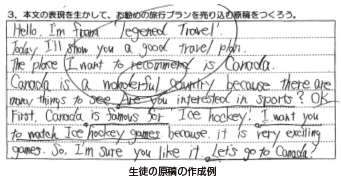
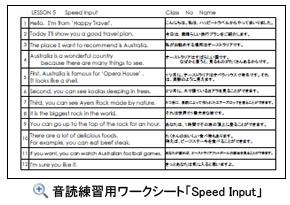
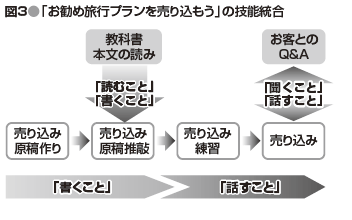 さらに、A社、B社のプレゼン後の「お客とのQ&A」では、お客がプランの内容について興味を持ったこと、さらに知りたいことなどを旅行社に質問し、追加情報を得る。ここでのお客と旅行社のやりとりは、「聞くこと」と「話すこと」が統合された活動である。しかも、この質疑応答はまったくの即興であり、学習者はそれまでに身につけた英語力を総動員して、コミュニケーションを図ることとなり、新学習指導要領で求められる一歩踏み込んだ言語活動となっている。
さらに、A社、B社のプレゼン後の「お客とのQ&A」では、お客がプランの内容について興味を持ったこと、さらに知りたいことなどを旅行社に質問し、追加情報を得る。ここでのお客と旅行社のやりとりは、「聞くこと」と「話すこと」が統合された活動である。しかも、この質疑応答はまったくの即興であり、学習者はそれまでに身につけた英語力を総動員して、コミュニケーションを図ることとなり、新学習指導要領で求められる一歩踏み込んだ言語活動となっている。