協会TOP > 英検 > THE EIKEN TIMES > アイデア・資料集 > 第2回 4技能を活用した「Group Work Reporting」活動
4技能統合の英語授業で使える! アイデア・資料集
第2回 4技能を活用した「Group Work Reporting」活動 |
| 前回は、「準備」→「練習」→「発表」という指導の流れの中で、主に「書くこと」「話すこと」の統合を中心にした言語活動を紹介した。第2回の本稿では、4技能をフルに活用して行う「Group Work Reporting」の活動を紹介する。 |
|
1. 「Group Work Reporting」とは? 「Group Work Reporting」は、教師が英語で話したストーリーをレポーター役の生徒が聞き取り、その内容を他の生徒に英語で伝えるグループ活動である。レポーター役を順次交代しながら、グループで協力して元のストーリーを再生し、その要約を英語で書いてまとめる活動である。「聞くこと」「話すこと」「書くこと」が統合された活動で、そこに「読むこと」も関連させ、4技能を統合した一連の学習となるものである。具体的な活動内容や指導の手順は後に紹介するが、まず、英語による「要約」や「Reporting活動」に注目する意義を考えたい。 2. なぜ「要約」や「Reporting活動」か?
「要約」や「Reporting活動」は、聞いたり読んだりした内容の要点を捉え、それらを英語を用いて書いたり話したりして表現するアウトプット活動である。それと同時に、伝える内容や伝えるために必要となる英語「表現」などが提供されているインプット活動でもある。伝える内容から用いる英語表現までを生徒が考え出さなければならないようなアウトプット活動とは異なり、学習者が必要に応じてインプット情報を活用しアウトプットを行うことができる活動である。いわば、インプットとアウトプットを学習者の中で有機的に結びつける活動であり、それを通して英語の定着を図るものである。 一方、中学校学習指導要領で示される「技能統合」では、聞いたり読んだりしたことについて、自らの考え(意見、感想、賛否など)を述べることができる生徒の育成が求められている。自らの考えを述べるためには、聞いたり読んだりした内容が理解できていることが前提であることは言うまでもない。さらに、話し手や書き手が述べた内容を引用したり、要約した上で自らの考えを述べたりすることは、話題や互いの考えの共通理解を図ることになり、円滑なコミュニケーションを図るために重要である。自己表現を急ぎ過ぎるあまり、互いの考えが共通理解されないまま自らの考えを伝えると、一方通行の情報伝達になり、真のコミュニケーションが行われたことにはならない。そこで、充実した双方向のコミュニケーションを可能にする土台固めのためにも、「要約」や「Reporting活動」による学習は意義があるものと考える。 3. 「Group Work Reporting」の指導過程
「Group Work Reporting」は、4~5名の小グループで行うReporting活動である。40名ほどのクラスでは、8~10グループに分かれて行うことになる。各グループは、1人ずつ「レポーター」役を決める。活動は次の(1)~(6)の手順で進めていく。 (1)「レポーター」は教室外に出て、教師が英語で話すまとまったストーリーを聞く(図1、2)。教室外で行うのは、教師の発話内容がレポーターの生徒にのみ伝わるようにするためで、それにより、レポーターとその他の生徒との間に情報のギャップが生まれ、内容を伝える必然性を作り出すことができる。(2)教師の話すストーリーを聞いた「レポーター」は教室内に戻って、自分のグループのメンバーに聞き取った内容を英語で伝える(図3)。いわば、「伝言ゲーム」のような活動である。しかし、「伝言ゲーム」と「Group Work Reporting」が異なるのは、伝える内容が単なる語句や短いメッセージではなく、ある程度まとまったストーリーであり、その内容を伝達する活動だという点である。伝えられた表現をそのまま用いて伝えることが目的ではなく意味の伝達を重視した活動であり、どのような英語表現を用いて伝えるかは、各レポーターに委ねられる。また、「伝言ゲーム」では、耳打ちしてリレー形式でメッセージを伝えるのに対して、「Group Work Reporting」では、レポーターが各グループのメンバー全員に、一度に伝える。(3)レポーター以外の生徒は、メモを取りながらレポートを聞く。 1人目のレポートが終了すると、(4)グループ内で順次レポーター役を交代して、グループメンバー全員が1度はレポーターとなり、教師から直接話を聞く機会を持つ。つまり、グループの人数分、レポートが繰り返し行われることになる。このとき、教師が話すストーリーは毎回同じ内容で、レポートの回を重ねるごとにグループに伝えられる情報が蓄積され、ストーリーの再生が可能となる。 (5)レポーターからの情報に基づいて取りためたメモや自ら聞き取った内容を統合し、グループで協力してストーリーの要約文を書いて完成させる。(6)その後、グループでまとめた要約内容を各グループの代表者が口頭で発表し、全員が英語の要約文を提出して活動は終了する。
「Group Work Reporting」は、伝える内容の長さや使用表現、活動時間を調節することにより活動の難易度を調整でき、様々な熟達度の学習者に対して実施可能な活動である。下の例は、中学3年生を対象に行った「Group Work Reporting」のストーリーである。ストーリーの内容や使用する英語表現は、生徒にとって難解なものではなく、どちらかと言えば易しめの英文であることが望ましい。また、学習者の理解度を増すために、教師がストーリーを伝えるときには、視覚情報を併せて提示するなどの工夫をする必要がある(かっこ内の数字は、同時に提示した絵の番号である)。
②「読むこと」「書くこと」の統合 先に示した(1)~(6)の指導過程に加え、生徒の要約文の質を高める学習機会を設けるために、(7)教師が伝えたストーリーをプリントにして読ませ、その英文を参考にしながら、各自の要約文を見直し、書き直すという活動を行うことができる。つまり、「Reporting活動」では、すべて口頭でやりとりされた内容を文章で提示し、生徒に読ませるのである。生徒は、オリジナルの文章を読み、新たに得た情報を付け加えたり、誤った英語表現を訂正したり、より良い英語表現に言い換えたりして、口頭での伝達時には気づかなかった様々な事柄について見直す機会を得ることになる。この「読むこと」と「書くこと」を統合した見直し活動は、生徒の学習状況に合わせて「Group Work Reporting」の直後に授業内で行ったり、家庭学習として行ったり、または別の授業で行うなど、様々な指導計画が立てられる。これにより、「読むこと」と「書くこと」が統合されることで、生徒の注意を意味内容と共に英語の表現にも向けさせることができる。 「Group Work Reporting」の指導過程と各技能の統合は、図4のようにまとめることができる。
③指導上のポイント レポーター役の生徒が教師の話を聞く時には<図4-(1)>、メモを取らせず各自の記憶に頼って、できる範囲でレポートするようにさせる。というのも、この活動では、一度のレポートでストーリーの詳細まで再生させることを期待しているわけではなく、グループで協力して情報を付け足しながら、徐々にストーリーの全容を明らかにしていく仕掛けになっているからである。生徒たちには、このような活動のねらいを、体験を通して理解させる必要がある。英語でうまく表現できなくても、これまでに身につけた表現に言い換えるなど、持てる力を総動員してレポートできるように支援したい。 一方、レポーター役の生徒がグループにストーリーを伝える時には<図4-(2)>、聞き手はメモを取りながらあらすじを捉えることとした。先に述べたように、1人のレポートですべての情報を伝えきることは不可能であり、レポーターからの報告を重ねるに従って、ストーリーの全容が明らかにされる過程を重視した。ストーリーを再生し要約文を書くときに、このメモの情報が重要となる。また、各メンバーは、一度は直接教師からストーリーを聞く機会があり、十分な情報が与えられる機会を全員に保証することができる。 これまでに中学校で実施した「Group Work Reporting」における生徒の学習を観察すると、生徒たちは、グループで要約をまとめて書く活動<図4-(5)>において、初めは意味内容に注目して情報の交換を行っているが、やがて英語表現(語順、文法の正確さ、適切な表現など)に注目が移り、要約文を仕上げていたようである。このことからも、生徒たちは、複数の技能を統合した活動を通して英語の意味と表現形式を結びつけながら学習を深めていることがわかる。 ④ストーリーの内容・教材作り 「Group Work Reporting」において、生徒の興味を高め積極的に活動に取り組ませるために、「教材」(ストーリー)は大切な役割を担う。何を教材に用いたらよいか、また、どのように教材を作成したらよいかが、教師の悩みどころである。中学校の授業において最も身近なのは教科書教材であり、教科書教材を中心に活用するのが有効である。ただし、指導のねらいや活動を実施する場面に応じて、教科書教材に情報を加えたり、題材に関連した新たな教材を用いることも効果的である。「教材の内容」やそれらを活用して「Group Work Reportingを実施する場面」は、下の表のようにまとめられる。
4. まとめ 「Group Work Reporting」の活動を始めると、当初は学習者のレポートがうまく行われないことがある。例えば、教師の話したストーリーの内容を生徒は大まかに理解できているのに、伝えようとすると英語が出てこない。どのように言ったらいいのか困ってしまい笑顔のまま黙ってしまったり、ジェスチャーのみで伝えようとしたり、あるいは、日本語をこっそり使用してレポートしてしまったりすることもあるであろう。そこが、教師の我慢のしどころであり、どのような支援が必要となるかを見極める機会と言えよう。
次回は、中学校編の最終回。生徒がインプットを生かしてアウトプットを行う、技能を統合した授業のアイデアを紹介する。
|
|
関連リンク
お知らせ
「THE EIKEN TIMES」は、2013年2月28日をもちまして、終了いたしました。
★「THE EIKEN TIMES」 終了のお知らせ
なお、一部コンテンツにつきましては、引き続き英検ウェブサイトでご覧いただけます。
上記、「『THE EIKEN TIMES』終了のお知らせ」 をクリックしてご覧ください。

 ①「聞くこと」「話すこと」「書くこと」の統合
①「聞くこと」「話すこと」「書くこと」の統合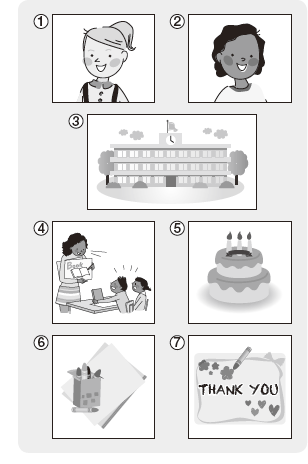
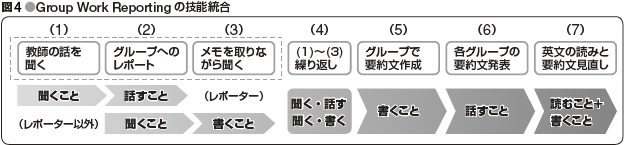
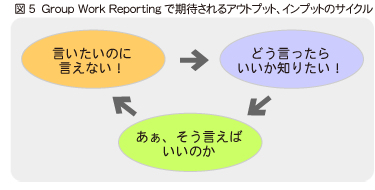 この活動では、学習者は「英語で言いたいけど言えない」「英語を聞いて理解できたけど、同じ内容をうまく英語で伝えることができない」などの状況に追い込まれる。しかし、この過程を経ることが学習者の英語力を高める上では重要であり、あえてこの活動に取り組んでいるポイントである。つまり、このように追い込まれた学習者にとって、教師が話すストーリーや他の学習者のグループでのレポート、その後に配布される英文などが、学習者が必要とする表現、言語知識を供給するインプットとして有効に活用される機会となり得る。ストーリーを伝えるというアウトプットが引き金となり、学習者のインプットへの注意や意識が高まり、表現や文法的な情報をより積極的に活用しようという態度に変化するのではないかと考える。「聞くこと」「話すこと」「読むこと」「書くこと」の4つの技能を有機的に関連づけつつ総合的に指導する「Group Work Reporting」を、学習者にふさわしい形にアレンジして、ぜひ、お試しいただきたい。
この活動では、学習者は「英語で言いたいけど言えない」「英語を聞いて理解できたけど、同じ内容をうまく英語で伝えることができない」などの状況に追い込まれる。しかし、この過程を経ることが学習者の英語力を高める上では重要であり、あえてこの活動に取り組んでいるポイントである。つまり、このように追い込まれた学習者にとって、教師が話すストーリーや他の学習者のグループでのレポート、その後に配布される英文などが、学習者が必要とする表現、言語知識を供給するインプットとして有効に活用される機会となり得る。ストーリーを伝えるというアウトプットが引き金となり、学習者のインプットへの注意や意識が高まり、表現や文法的な情報をより積極的に活用しようという態度に変化するのではないかと考える。「聞くこと」「話すこと」「読むこと」「書くこと」の4つの技能を有機的に関連づけつつ総合的に指導する「Group Work Reporting」を、学習者にふさわしい形にアレンジして、ぜひ、お試しいただきたい。