協会TOP > 英検 > THE EIKEN TIMES > アイデア・資料集 > 第3回 技能統合の授業動
4技能統合の英語授業で使える! アイデア・資料集
第3回 技能統合の授業動 |
| 中学校編最終回では、検定教科書を「読み物」として扱い、教科書の内容を英語で話して伝える、技能統合の授業を提案する。 |
|
1. 「世界面白ニュース」プレゼンテーション 世界の珍しい話題や驚きのニュースを扱うテレビ番組が人気を得ているようである。奇想天外な出来事や日本ではあまりなじみのない話題について、映像を交えたレポートに興味を持つ視聴者が多いのであろう。そこで、それと同様の活動を教室内で英語を用いて行おうとしたのが、「世界面白ニュース」のプレゼンテーション活動である。学習者は、英字新聞を読んで「面白ニュース」を探し出し、その内容を英語でわかりやすく紹介する。 具体的には、学習者は、①山積みされた多くの英字新聞の中から、見出しや写真などを頼りに「面白ニュース」となりうる記事を求めて新聞を読む。②「面白ニュース」の記事が見つかると、聞き手がわかりやすいように内容を要約し、発表原稿を書いてまとめ、③記事内容のプレゼンテーション練習に取りかかる。④プレゼンテーションでは、言葉だけではなく、内容理解を助ける視覚的な情報も同時に提示して発表し、聞き手の理解を促すような工夫を行う。⑤発表後には、聞き手との間で英語による質疑応答をしたり、記事の内容に対する感想を述べ合ったりする。 この活動では、読んだ内容を書いてまとめ、話して発表するという順で、複数の技能統合がなされる。この活動における技能統合を学習の流れとともに整理すると、図1のようにまとめられる。
発表者が選んだ記事の多くは、驚きの情報が含まれ、聞き手は興味を持って楽しんで聞いていた。ただし、これは、中学生を対象とした実践ではなく、私の勤務校である大学の英語授業で行っている活動の一つである。「なんだ、大学生か! 中高生にはしょせん、無理な活動だ!」と失望される方もいるかもしれない。しかし、最終回である本稿のねらいは、「読むこと」と「書くこと」「話すこと」を統合した発表の活動(①~④)と、そのあとの「聞くこと」「話すこと」を統合した英語による即興的なやりとり(⑤)を行う活動を、中学生対象の活動へ「リフォーム」しようとするものである。最後までおつき合いいただければありがたい。
2. 「世界面白ニュース」プレゼンテーションが目指すもの
大学生を対象にした「世界面白ニュース」プレゼンテーションの活動で、①「記事選び」②「内容の要約」で行われる「読み」を比較すると、発表者は、①で自らが内容理解をするために読むのに対して、②では、内容を誰かに伝えるための「読み」が行われることになる。つまり、要約するための「読み」では、表面的な理解にとどまらず、書かれた内容を整理してより深く理解することが必要とされる。また、英語表現にも十分注意を向ける必要が出てくる。このように、「読むこと」と「書くこと」「話すこと」の技能統合によって「読み」の質が向上し、英語による発信の下地づくりが行われることになる。 ③では、聞き手の理解度を考慮した発表となるように準備が進められる。④のプレゼンテーションでは、一方通行の情報伝達にならないよう、聞き手の理解を確認しながらの発表や、難しいと思われる表現の言い換え、ジェスチャーや視覚情報の活用など、聞き手に理解可能なアウトプットを提供できるよう発表者が工夫をする良い機会となる。その上で、⑤プレゼンテーションの内容について、質疑や感想のやりとりを行うことにより、即興性を必要とする「聞くこと」「話すこと」の統合がはかられる。 複数の技能を統合して「世界面白ニュース」プレゼンテーションの一連の活動を行うことにより、上記のような効果が期待できる。同様の活動が中学生にも可能となれば、中学生の英語の熟達度に見合った「読み」の質が高まり、英語で発信する力の養成へとつながっていくのではないかと期待する。 3. 中学校英語教科書に見るプレゼンテーション 現行6社の中学校英語教科書では、「発表しよう」「紹介しよう」「スピーチしよう」というような、英語によるプレゼンテーションを扱ったページが多く見られる。例えば、「偉大な人物」や「日本文化」などは、複数の教科書で中学3年生の題材として取り上げられている(表1)。
例えば、SS 3 My Project 8の「伝統文化を説明しよう」という活動では、生徒が直前の課で茶道や伝統的な遊びなどの日本の文化についての題材を学習したあと、地域の伝統的な行事や習慣について調べ、英語の発表原稿を書き、最終的に英語による発表を行うという設定になっている。つまり、先の大学生の活動同様、「英語で発表」を行う活動は、中学の英語教科書でも扱われている課題なのである。ただ、異なるのは、「世界面白ニュース」の活動が読んだ内容を英語で発表するのに対して、中学校英語教科書の「伝統文化紹介」の活動は、読んだ文章を参考にして、生徒自らが考えた内容を英語で発表するという点である。 4. 読んだ内容を英語で伝える「サマリー・テリング」 ①自己表現活動の指導過程リフォーム
②中学生用「読み物教材」の発掘 大学生の活動では、様々な読み物の活用が可能であった。しかし、中学生の英語の熟達度に合った読み物教材を手軽に調達することは簡単ではない。教師やALTの自作教材やウェブ上の使用可能な教材を丹念に探すことも考えられるが、ここでは、生徒の英語の熟達度に合い、しかも、手軽に活用できる「読み物教材」として、「検定教科書」の使用を提案する。通常は、6社から出ている検定教科書のうち、1社のみを使って指導しているが、この活動では、採用している教科書以外の5社の教科書、さらには、改訂前に使用していた旧版の検定教科書教材の中で「日本文化」について扱っている課を「読み物」教材として活用して読み、内容を要約して「書いて」まとめ「話して」伝える教科書内容の「サマリー・テリング」を行うのである。それにより、「世界面白ニュース」の活動と同様に、英語で発信することを意識した「読み」「書き」を行わせ、英語によるプレゼンテーションやその後のコミュニケーションへとつなげていくことができる。
現行版中学校英語教科書では、どれほどの課で「日本文化」について扱っているであろうか。表2-1からわかるように、様々な話題が数多く扱われており、読み物教材として十分な数と種類を提供できる。また、「世界の偉人」に関わる題材も同様に幅広く扱われていることがわかる(表2-2)。しかも、これらは、いずれも検定教科書の教材であり、どの教材を用いても扱われる文法事項、語彙ともに中学生に合った内容となっている。さらに、異なる学年の教材が存在し、これらの教材を生徒が自由に選んで活用すれば、自らの英語の熟達度に合った読み物が選択でき、個に応じた英語学習を進めることができる。 ③中学生対象の活動へのリフォーム これら教科書教材の幅広い活用と、その内容の「サマリー・テリング」により、先の大学生を対象としたプレゼンテーション活動が、中学生を対象とした活動へとリフォームできることになる。図3に示したように、生徒は、①表2に示した教材から、自らの興味や教材の難易度により読み物を決定し、読む。②聞き手がわかりやすいように内容を要約し、「サマリー・テリング」の原稿を書いてまとめ、③「サマリー・テリング」の準備に取りかかる。④「サマリー・テリング」では、必要に応じて内容理解を助ける絵などを同時に提示して発表し、聞き手の理解を促すような工夫を行う。発表は全員の前で行ったり、グループ内で行ったりするなど様々な形態が考えられるが、学習者の情意面への配慮や学習者の活動量を増やすことを考えると、「ペア活動」が有効である。ペア内で、発表者と聞き手の役割を交代しながら、パートナーを代えて、繰り返し何度もプレゼンテーションを行わせる。⑤発表後の英語によるやりとりでは、発表者が事前に準備した聞き手の内容理解を確認するQ&Aや、聞き手からの内容についての質問、発表された内容への簡単なコメントなど即興的な英語のやりとりを行う。 5. まとめ 現行版の中学校英語教科書では、各教科書とも「Project」「Activity」「Multi Plus」など名称は異なるが、生徒が英語による発表を行う課題を設けている。そのすべてにおいて、ここで紹介したような、「サマリー・テリング」まで含めた学習を行う時間的余裕はないかもしれない。しかし、機会をとらえて、扱っている教科書の題材に関連する様々なほかの教科書教材を読み、「サマリー・テリング」や自己表現を重点的に行う指導計画を作成してもよいのではないだろうか。生徒は、重点的に扱われた題材に関連する語彙や表現が豊富になり、その中の一部が定着し身についていくと期待できる。 さて、早速、様々な教科書を用意して「日本文化紹介」プレゼンテーションを授業に取り入れてみようと思っていただいた読者の皆さん、教科書1冊の価格は、ほぼ缶ビール1本程度。各社の教科書を準備して、旧版も含めた全21冊からなる全教科書完備ライブラリーを作り、指導計画づくりに取りかかってみてはいかがだろうか。 3回にわたる連載に最後までおつき合いいただき、ありがとうございました。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
次回からは、高等学校編を取りあげます。
関連リンク
お知らせ
「THE EIKEN TIMES」は、2013年2月28日をもちまして、終了いたしました。
★「THE EIKEN TIMES」 終了のお知らせ
なお、一部コンテンツにつきましては、引き続き英検ウェブサイトでご覧いただけます。
上記、「『THE EIKEN TIMES』終了のお知らせ」 をクリックしてご覧ください。

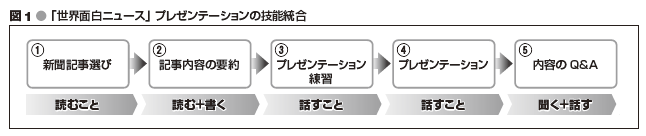

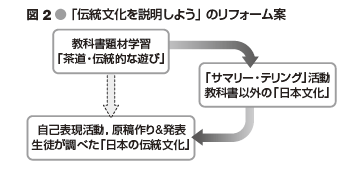 中学生の「伝統文化を説明しよう」の活動は、伝統文化を扱った「本文の理解」から「自己表現」へつながる、一見スムーズな活動の流れである。しかし、実際に指導してみると、生徒にとって「理解」と「表現」の間には隔たりがあり、教科書内容は理解できていても、自分で紹介しようとする内容はなかなか英語で表現できないという生徒は少なくない。そこで、そのギャップを埋めるために、読んだ内容を要約(サマリー)して英語で話して(テリング)紹介する、いわば、「サマリー・テリング」とでも呼ぶ活動を行うことは効果的である。具体的には、既に学習した教科書本文とは別の「日本文化」についての英語の文章を読み、その内容の「サマリー・テリング」を行う。それによって、段階的に自己表現活動に向けた学習を進めていけるようになる。
中学生の「伝統文化を説明しよう」の活動は、伝統文化を扱った「本文の理解」から「自己表現」へつながる、一見スムーズな活動の流れである。しかし、実際に指導してみると、生徒にとって「理解」と「表現」の間には隔たりがあり、教科書内容は理解できていても、自分で紹介しようとする内容はなかなか英語で表現できないという生徒は少なくない。そこで、そのギャップを埋めるために、読んだ内容を要約(サマリー)して英語で話して(テリング)紹介する、いわば、「サマリー・テリング」とでも呼ぶ活動を行うことは効果的である。具体的には、既に学習した教科書本文とは別の「日本文化」についての英語の文章を読み、その内容の「サマリー・テリング」を行う。それによって、段階的に自己表現活動に向けた学習を進めていけるようになる。