協会TOP > 英検 > THE EIKEN TIMES > アイデア・資料集 > 第6回(最終回) 英語を苦手とする生徒を対象とした技能統合型活動
4技能統合の英語授業で使える! アイデア・資料集
第6回(最終回)
英語を苦手とする生徒を対象とした技能統合型活動
|
|
1. はじめに 高等学校編の第3回(最終回)となる今回は、英語を苦手とする生徒を対象とした技能統合型活動について紹介する。高校には入学試験による生徒の振り分けがあり、学校ごとに生徒の学習到達度の差が非常に大きい。学校によってはほとんどの生徒が英語を苦手としており、技能統合型活動の実施が難しい場合も多いだろう。しかし、学習指導要領はすべての高校を対象としており、技能統合型活動は英語を苦手とする生徒が大半を占める学校でも、例外なく推進されなければならない。では、英語を苦手とする生徒に対してはどのように技能統合型活動を行っていけばよいだろうか。今回は、この難問について考えていきたい。 2. 英語を苦手とする生徒と向き合うために ~「動機付け」と「適切な支援」~
英語を苦手とする生徒たちと向き合うときに、まず考えなければならないのは、教師による「動機付け」と「適切な支援」であろう。いくら素晴らしい技能統合型活動を計画しても、生徒が十分に動機付けられていないのでは意味はなく、教師が適切な支援を与えて生徒の学習を方向づけなければ、生徒の学習意欲は継続しないと考えられる。 通常の教科書本文に基づいた指導において、動機付けと適切な支援を意識しながら展開する技能統合型活動の一例を、表1にまとめてみた。いずれも目新しいものではないが、著者の勤務校の英語を苦手とする生徒たちが、特に意欲的に取り組んでいるものである。
ここでは、動機付け方略の1つとして、Self-Determination Theory(自己決定理論: 以下SDT)に基づいた動機付けから多くのヒントを得ている。SDTは、動機付けを「自己決定の段階」という連続体で捉えると同時に、「動機付けを高める要因」を想定している理論である。SDTでは、すべての人が生得的に持っている心理的欲求として、「自律性・有能さ・関係性」への欲求を挙げ、これらが満たされる環境において動機付けが高められるとされている(Deci&Ryan,2002)。英語教育におけるSDTに基づいた動機付けについては、近年、日本でも複数の研究がなされており、その代表者の1人である廣森(2006)は、「意図的に自律性、有能さ、関係性を満たす働きかけを包括した英語学習活動を行うことで、学習者の動機付けを高めることができる」と述べている。 また、生徒の学習に対する適切な支援に関しては、Scaffoldingの考え方をヒントにすることができる。Scaffoldingとは、建築現場での「足場がけ」という意味であるが、学習の分野ではWood et al.(1976)が「子どもや初心者が、援助がなくてはできない問題を解決したり、タスクを実行したり、目標を達成したりすることを可能にする援助」と定義している。Scaffoldingの具体的な機能例については、図1を参照されたい。
3. お気に入りの歌詞紹介 ~My Favorite Lyrics~ 次に、動機付けと適切な支援を意識した技能統合型活動の例を、さらに2つ挙げる。いずれも教科書本文指導という枠組みから離れた形で行う技能統合型活動だが、生徒たちが非常に意欲的に取り組んだ活動であるので紹介したい。 まず、生徒がお気に入りの英語の歌詞を紹介し合うことを目的とした活動“My Favorite Lyrics”を紹介する。この活動では、SDTに基づいた動機付けをヒントにして、生徒が自ら題材を選択した上で調べ、好きな音楽の紹介を通じ、ほかの生徒とのつながりを確認し、歌詞の内容理解で達成感を得る、という過程を通じた動機付けを試みている。 この活動では、英語を苦手とする生徒に対しては、洋楽ではなく日本人が歌う曲(邦楽)に含まれる英語の歌詞を題材にするよう勧めている。洋楽を用いたディクテーションは一般的によく行われている活動であるが、英語が苦手な生徒たちに、洋楽の英語を聴き取らせることは非常に難しい。邦楽に登場する英語の歌詞は、しばしば洋楽の英語よりも聴き取りやすいものが多く、メッセージ性が強いフレーズも多い。 【手順】 ①生徒に、好きな洋楽もしくは邦楽に含まれる英語の歌詞をワークシートに記入させる。この作業は、家で歌詞カードやウェブサイトを見て歌詞を書かせたり、もしくは実際に家で聴いて歌詞を書き取らせたりするなどの宿題にしてもよい。 ②記入した英語の歌詞を、辞書などを活用して日本語に訳させ、ワークシートに作成した和訳や調べた単語を記入させる。また、その歌詞が好きな理由など、歌詞に関するコメントを英語で書かせる。ワークシートは教師がいったん回収し、記入された和訳やコメントに対してフィードバックを加える。 ③生徒が取り上げた曲のうち、CDなどの音源が準備できるものはクラスで共有する。曲の当該部分を流して、個人またはペアで歌詞をワークシートに書き取らせて、日本語に訳させる。その後、その歌詞を提案した生徒に、歌詞の和訳や使われている単語の意味、歌詞に関する自らのコメントを紹介させる。最後に、それぞれの生徒に、紹介された歌詞に関するコメントを英語で記入させる。 なお、この活動は、複数回の授業にわたる帯活動にすることもできる。
4. Paper Counseling 次に紹介する、Paper Counseling(紙上カウンセリング)は、ある生徒が英語で書いた「悩み」について、ほかの複数の生徒が英語でアドバイスを加えていくという、主に「読むこと」と「書くこと」を統合した活動である。特徴としては、誰が書いたかわからないように無記名でワークシートをリレーしていく点が挙げられる。自己表現をあまりしたがらない内向的な生徒でも、誰が書いたかわからない仕組みにすることで、より積極的な取り組みを促すことができる。また、「あなたの悩みは何ですか」といった、個人的な質問に対し、生徒たちは日本語だとなかなか心の内を書いてはくれないが、英語だと心を開いて書いてくれる場合がしばしばあり、このような点からも生徒の積極的な取り組みが期待される。具体的には次のような手順で活動を進めていく。 【手順】
②ワークシートをシャッフルして、ほかの生徒にランダムに配布する。それぞれの生徒は英語で記入された「悩み」を読解し、辞書などを使いながら英文3~4行のアドバイスを書く。 ③ワークシートをもう一度シャッフルし、別の生徒にランダムに配布する。それぞれの生徒は英語で記入された「悩み」、ならびに既に記入されたアドバイスを読解し、辞書などを使いながら英文2~3行のアドバイスをさらに書く。 ④最初に「悩み」を書いた生徒にワークシートを返却する。ワークシートを返却された生徒は、記入された2つのアドバイスを読解し、感想を英語で記入する。 生徒が自らの力で英語によるアドバイスを書くことが困難な場合は、あらかじめアドバイスに使用できそうなフレーズなどを提示しておく。また、必要な場合は、生徒がコメントやアドバイスを書く度に回収し、教師が文法的なフィードバックを加えてから、別の生徒にワークシートを配布してもよいだろう。 生徒からは、「普段は日本語で書きづらいことも、英語だと素直に書くことができる」という声や、「英語で書かれたアドバイスを理解したいから、必死に調べながら読んだ」という声が寄せられ、生徒が積極的に取り組んだことが伺える。 5. まとめ 今回は、英語を苦手とする生徒を対象とした技能統合型活動について、動機付けと教師による支援という観点を踏まえて紹介した。英語を苦手とする生徒たちが抱える課題は様々であり、特効薬は存在しないだろう。英語力に関わらず、すべての生徒が技能統合型活動を通じて「英語使用の楽しさ」を実感できるよう、著者も引き続き実践と省察を繰り返していきたい。 3回にわたる高等学校編の連載をお読みいただき、ありがとうございました。
|
|
関連リンク
お知らせ
「THE EIKEN TIMES」は、2013年2月28日をもちまして、終了いたしました。
★「THE EIKEN TIMES」 終了のお知らせ
なお、一部コンテンツにつきましては、引き続き英検ウェブサイトでご覧いただけます。
上記、「『THE EIKEN TIMES』終了のお知らせ」 をクリックしてご覧ください。

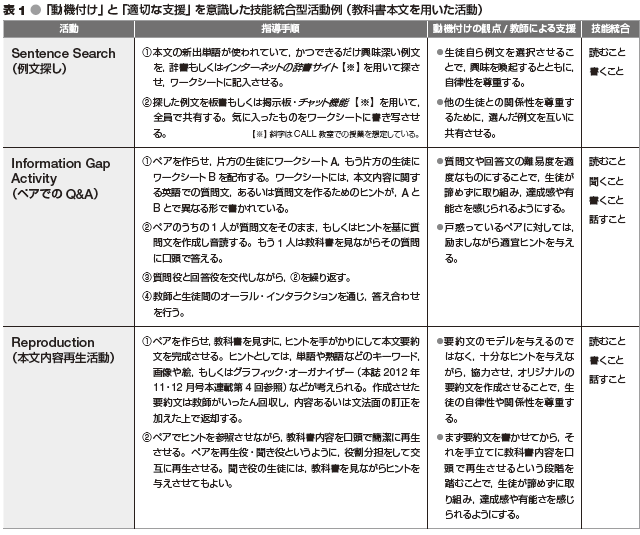
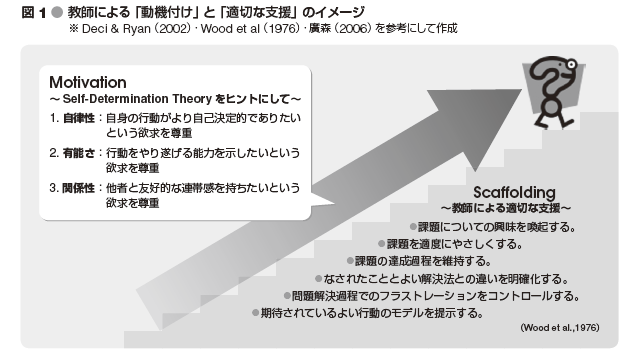
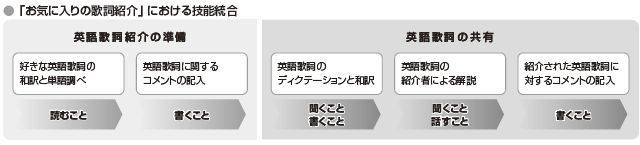
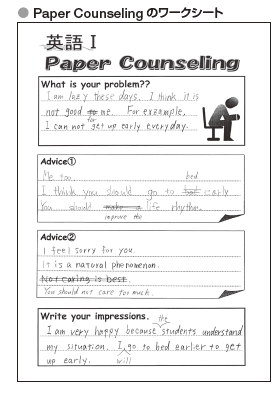 ①それぞれの生徒にワークシートを配布し、“What is your problem?”(あなたの悩みは何ですか)という質問に対する回答として、辞書などを使わせながら3~4行の英文を書かせる。ワークシートに記名はさせず、教師にしか個人が特定できないようにナンバリングをしておく。
①それぞれの生徒にワークシートを配布し、“What is your problem?”(あなたの悩みは何ですか)という質問に対する回答として、辞書などを使わせながら3~4行の英文を書かせる。ワークシートに記名はさせず、教師にしか個人が特定できないようにナンバリングをしておく。