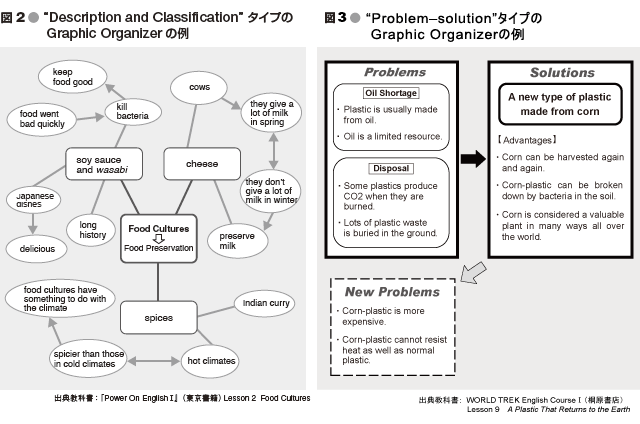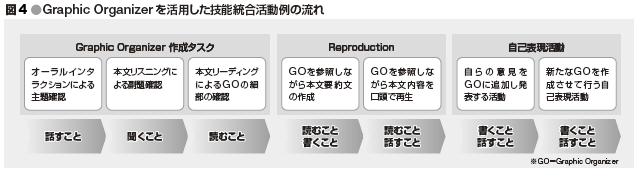協会TOP > 英検 > THE EIKEN TIMES > アイデア・資料集 > 第4回 教科書本文指導における技能統合 ~Graphic Organizerを活用して~
4技能統合の英語授業で使える! アイデア・資料集
第4回 教科書本文指導における技能統合 ~Graphic Organizerを活用して~ |
|
1. はじめに 本連載第4回~第6回では、高等学校において複数技能を統合して行う授業の具体的な活動例、指導手順例、指導に必要なワークシート例などを紹介していきたい。 さて、高校における複数技能を統合した授業というと、「英語Ⅰ・Ⅱ」などで通常行われている「教科書に基づいた活動」ではなく、ディベートやタスク活動などといった「イベント型の活動」を想像する方も多いのではないか。確かに、教科書本文指導という制約がない分、そのような「イベント型の活動」のほうが、より複数技能を統合しやすいかもしれないが、通常行われている教科書本文指導も、ひと工夫加えることで技能統合型活動にすることができる。高等学校編の初回となる今回は、普段の授業において役に立つ、教科書を用いた技能統合型活動のアイデアを紹介する。 2. 高等学校学習指導要領に見る4技能統合
技能統合型活動について具体的に紹介する前に、新学習指導要領(平成25年施行)における、4技能統合に関する記述を確認する。 中学校学習指導要領と同じく、高等学校学習指導要領においても「4技能を統合的に教えること」は決して新しい発想ではなく、現行の学習指導要領(平成15年施行)においても重視されていたものである。しかし、現行の学習指導要領では、「英語Ⅰ・Ⅱ」以外は「オーラル・コミュニケーション」、「リーディング」、「ライティング」など4技能を別々に教える技能別編成になっていた。その結果、吉田(2009)も指摘する通り、「英語Ⅰ・Ⅱ」は統合的科目として設定されたにもかかわらず、「オーラル・コミュニケーション」という科目が別にあるために、「英語Ⅰ・Ⅱ」は、しばしば「文法訳読」の科目ととらえられていた。この点を改善すべく、新学習指導要領では、「コミュニケーション英語Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」という統合的科目が新たに編成され、4技能を統合的に指導することがより明確に示されているのである。 高等学校学習指導要領解説編に述べられている技能統合型活動について、全員の必修科目である「コミュニケーション英語Ⅰ」に関する記述をまとめると、次の表のようになる。
3. Graphic Organizer ~教科書本文を用いた技能統合型活動のためのツール~ 表1で例示されているような技能統合型活動を、教科書を用いた普段の授業で実施するために役に立つツールの1つが、Graphic Organizerである。 Graphic Organizerは、もともと認知科学の分野で発展した考え方で、近年はSLA(第二言語習得)の分野でも研究が進んでいる。SLAの分野におけるGraphic Organizer 研究で著名なWilliam Grabe は、Graphic Organizer を“visual representation of information in the text”(Jiang & Grabe, 2007)と幅広く定義しており、具体例としてはライティング指導などでよく使われるマッピング(セマンティック・マップ)なども含まれる。 英語授業においては、Graphic Organizerはすでに様々な指導場面で活用されていると考えられるが、Graphic Organizerは、計画的・系統的に活用することにより、教科書本文を用いた技能統合型活動を効果的に実施するためのツールとなる。 4. Graphic Organizerを活用した技能統合型活動例 次に、教科書本文指導における、Graphic Organizerを活用した技能統合型活動の例を述べていく。 ①Graphic Organizer作成タスク 【手順】 ①パートもしくはレッスンのメインテーマについてオーラル・インタラクションを行い、生徒と教師の間でスキーマ(背景知識)を共有する。使用するGraphic Organizer のタイプ(後述参照)を決定した上で、メインテーマ(下の図では“Thesis Statement”の部分)を記入する。 ② 1パート(もしくは1レッスン)の本文音声を聞かせ、パラグラフもしくはパートごとのサブテーマ(下の図では“Evidence1・2・3”の部分)の項目を書き加えていく。書き加えた事項について、教師と生徒間でオーラル・インタラクションを通じて確認する。 ③ 1パート(もしくは1レッスン)の本文を読ませ、さらに細かい項目を書き加えていく。書き加えた事項について、教師と生徒間でオーラル・インタラクションを通じて確認し、完成版のGraphic Organizerを共有する。 ※英語が得意な生徒たちに対しては、ヒントを与えず1からGraphic Organizerを作成させてもよい。逆に英語が苦手な生徒たちに対しては、Graphic Organizerの枠のみをあらかじめ示し、空所を埋めさせていくような活動にしてもよい。
②Reproduction(本文内容再生タスク) ●完成したGraphic Organizerを参照させながら、教科書を見ずに教科書内容を口頭で再生させる。ペアを作り、1人が再生役、もう1人が聞き役となる。本文内容を再生させる際に、Graphic Organizerに記載されている英文や語句は原則的にすべて使用させ、聞き役の生徒はGraphic Organizerの英文や語句の使用をチェックしながら聞く。 ●生徒の習熟度に応じ、聞き役の生徒にヒントを与えさせたり、2人で協力して本文内容を再生させるペア・ワークにしたりすることもできる。 ●口頭ではなく、Graphic Organizerを参照させながら、本文要約文を書かせて再生する活動にすることもできる。 ③自己表現活動 ●本文内容に対する自らの意見や感想を、完成したGraphic Organizerに追加の項目として書き込ませていく。自らの意見や感想の項目を書き込ませる際は、違う色のペンを使わせるとわかりやすい。この作業は個人で行わせてもよいが、教師と生徒間でオーラル・インタラクションを行い、意見や感想を共有しながら、Graphic Organizerに追加の項目を書き込ませていくこともできる。 ●追加の書き込みがなされたGraphic Organizerを参照させながら、本文内容に対する自らの意見や感想を英語で書かせ、口頭で発表させる。 ●本文内容に関連するトピックで自己表現活動(パラグラフ・ライティング/ディスカッションなど)をさせる際に、すでに作成したGraphic Organizerを参照させながら新たなGraphic Organizerを作成させ、自己表現活動を進めるための手立てにさせることもできる。 5. Graphic Organizer活用のヒント ①様々なGraphic Organizerのタイプ 英文は通常複数のパラグラフで構成されるが、それぞれのパラグラフの構成は、何かを「主張」するタイプのものであったり、「列挙」するタイプのものであったりと様々である。前述の活動例で紹介した英文は、1つのテーマについて「主張」するタイプのパラグラフ構造を持つものであったが、英文がいつも前述の例のようなパラグラフ構造を持つとは限らない。よって、英文のパラグラフ構造によって異なるタイプのGraphic Organizerを使用する必要がある。 Graphic Organizer と英文のパラグラフ構造の関係については、Grabe(2009)が興味深い主張を行っている。GrabeはモデルとなるGraphic Organizerのタイプを複数提示した上で、Graphic Organizer の活用を通じて様々な種類のパラグラフ構造を理解することの重要性を述べている。 教科書本文を読み始める前に、レッスン全体のスキミングを通じてパラグラフ構造を分析させ、どのタイプのGraphic Organizerを使用するか考えさせることは、非常に効果的な活動だろう。近年の大学入試問題においても、英文のパラグラフ構造の分析が求められるような問題があるので、このような活動は、入試対策にもなると考えられる。 2 ICTの活用Graphic Organizerをさらに効果的に授業内で使用する方法として、ICTの活用が挙げられる。例えば、プロジェクターを用いてパワーポイントでGraphic Organizerを提示すれば、より効果的に生徒の発話を促すことができる。また、一度Graphic Organizerのパワーポイントスライドを作成してしまえば、時間をかけずに、様々な活動で同じGraphicOrganizerを提示することができる。
②ICTの活用 Graphic Organizerをさらに効果的に授業内で使用する方法として、ICTの活用が挙げられる。例えば、プロジェクターを用いてパワーポイントでGraphic Organizerを提示すれば、より効果的に生徒の発話を促すことができる。また、一度Graphic Organizerのパワーポイントスライドを作成してしまえば、時間をかけずに、様々な活動で同じGraphicOrganizerを提示することができる。
6. まとめ 今回は、通常行われている教科書本文指導において、Graphic Organizerが技能統合型活動を実施するためのツールになるということを紹介した。ここで紹介できなかったGraphic Organizerの具体例やワークシート、そして実際の指導で使用したパワーポイントファイルなどは、英検ウェブページ内にある本連載のコーナーに提示するので、ご活用いただきたい。 次回は、教科書本文指導という枠組みから離れた形で行う技能統合型活動について紹介する予定である。
|
|
関連リンク
お知らせ
「THE EIKEN TIMES」は、2013年2月28日をもちまして、終了いたしました。
★「THE EIKEN TIMES」 終了のお知らせ
なお、一部コンテンツにつきましては、引き続き英検ウェブサイトでご覧いただけます。
上記、「『THE EIKEN TIMES』終了のお知らせ」 をクリックしてご覧ください。